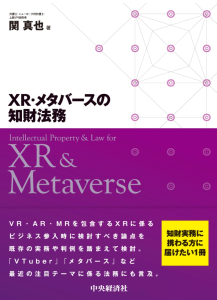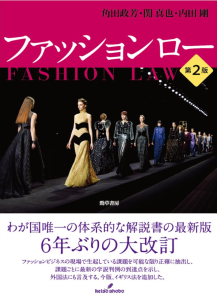【キーワード】
米国 不正競争 パブリシティ権 声の権利 ものまね 広告 連邦法と州法による保護の重複関係 著作権法と不正競争防止法による保護の重複関係
本判決:Sinatra v. Goodyear Tire & Rubber Co., 435 F.2d 711 (1970).
【事案の概要】
原告・控訴人Nancy Sinatraはプロのエンターテイナーである。彼女は「These Boots Are Made For Walkin’」というタイトルの楽曲を録音し、その楽曲は人気を博した。この楽曲の音楽、歌詞及び編曲は、Criterion Music社を著作権者として著作権登録された。
被告Goodyear Tire and Rubber Company及び被告Young and Rubicam, Inc.(広告代理店)は、被告Goodyear社が製造するタイヤの説明用語として「wide boots」というフレーズを造語するというアイデアを着想した。この「wide boots」をテーマとした大規模な広告キャンペーンの一環として、被告らは、画面に登場せず名前も明らかにされていない女性歌手の声と、「These Boots Are Made For Walkin’」の音楽及び替歌を用いた背景音楽を中心とする6つのラジオ及びテレビコマーシャルを制作し、放映した。
訴状において、原告は次のとおり主張している。
- 当該楽曲は原告によって非常に人気となったため、それによって彼女の名前が識別されるようになったこと
- 彼女は当該楽曲との関連をもって最もよく知られていること
- 被告らが使用した楽曲及び編曲がセカンダリーミーニングを獲得したこと
- 被告らが、原告の声及びスタイルを意図的に模倣する歌手を選定したこと
- 当該テレビCMに一瞬だけ登場する少女たちの外見及び服装は、原告の特徴及び服装を利用したものであること
原告は、これらの行為はすべて、原告が当該CMに参加したものと大衆を欺くことを目的として意図的に行われたものであると主張している。
また、原告の主張によれば、被告Young and Rubicam社は、以前、Goodyear社の代理店として彼女を起用しようと彼女のエージェントに接触したが、契約は締結されなかった。
原告は、被告らに対し、損害賠償及び当該CMの使用差止め等を請求した。
原審は次のとおり認定及び判断し、被告らの求める略式判決をした。
- 「These Boots Are Made For Walkin’」の実演は、本件における2つのラジオCM及び4つのテレビCMのいずれにおいても匿名である。すなわち、いずれのCMについても、特定の個人の実演又は声を体現していることを示す音声的又は視覚的な表現、主張及び推論は存在しない。
- 被告はパッシングオフ(詐称通用)を行なっていない。すなわち、被告らは、そのCMが原告又は他人の作品であると大衆を誤信させるようなことはしていない。模倣したということだけでは、訴訟原因にはならない。
【裁判所の判断】
第9巡回区控訴裁判所は以下のとおり述べ、原審の判断を支持した。
はじめに、本件は著作権侵害訴訟ではないということを念頭に置く必要がある。著作権者はCriterion Music社である。同社は、「These Boots Are Made For Walkin’」の音楽、歌詞及び編曲の著作権を保有していた。1967年3月3日、問題となっているCMの制作に先立ち、Criterion社は被告Goodyear社を代理するYoung and Rubicam社との間で、「[Criterion社]が保有又は管理する編曲、音楽及び/又は歌詞を含む」楽曲の利用許諾に関する契約書を締結した。
また、本件においては、原告の声の実際のテープその他の録音物が再生されたわけではない。 Nancy Sinatraの歌唱であると偽って表示されたわけでもない。
カリフォルニア州法では、不正競争は法典 (code) において定義されている。この定義によれば、不正競争とは、「違法、不公正又は欺瞞的な商慣行及び不公正、虚偽又は誤解を招くおそれのある広告」を意味し、これらを含むものとされる。
同法における裁判例を検討したところ、本件と不正競争に関する大多数の裁判例との間には、事実関係における明白な相違点があることが即座に明らかとなった。Nancy SinatraとGoodyear Tire Companyとの間には競争関係がない。控訴人はタイヤ業界に属しておらず、Goodyear社はレコードを販売していない。名称、スローガン、手段その他の公正な取引慣行を偽装することによって、被告が原告の作品を自社の作品であるとパッシングオフ(詐称通用)した事実もない。
Lahr事件及びSim事件の被告らは、自らが著作権を有する素材の取引をしたわけではない。詳しく言い換えれば、Lahr事件及びSim事件の原告らは、純粋な音、すなわち彼らの個々の声の特徴が、「セカンダリーミーニング」を獲得したと主張していたのである。そこで求められた保護は、本件において求められた、著作権のある歌詞、メロディ及び編曲と音の組み合わせに対する保護ではなかった。本件における控訴人の主張は、彼女の歌声が独特な個性を有するということではなく、彼女の歌声が、音楽、歌詞及び編曲と結びついて、彼女を人気のある人物として認識させるものとなっているため、その歌声は保護されるべきだというものである。しかしながら、著作権で保護される後者の項目については、彼女には権利がなかった。おそらく、彼女は [当該楽曲] を歌うために著作権者の許可を得る必要があり、また、自分の好みや才能に合わせてその曲を編曲する必要があった。もし彼女が、他の誰もが当該楽曲を利用することを排除し、当該楽曲に係る彼女の「セカンダリーミーニング」を模倣できないようにすることを望んだのであれば、著作権者からその権利を購入することも可能であった。もし、放送されたのが、彼女にとっては残念ながら他人が権利を保有し、被告らに利用許諾がされていた「彼女の楽曲」ではなく、他の楽曲であったとしたら、彼女の声と演劇スタイルが識別可能となっていたかどうかは疑問である。もっとも、この問題は、いま、当裁判所の前に提起されているものではない。
連邦最高裁判所は、州が連邦特許法を直接侵すことができないのと同様に、州法が連邦の目的と衝突する場合において、州が不正競争に対して当該州法を執行するという名目のもと間接的に連邦特許法を侵すこともできないことを明確にした。本件において、被告らは、当該楽曲及びその全ての編曲の利用許諾を得るために、著作権者に対して非常に多額の支払いをした。原告は、彼女が主張したセカンダリーミーニングを保護したであろう当該著作権を求めず、また、取得もしなかった。州法の下で損害賠償や差止めによる救済が認められるとすれば、連邦法との衝突は避けられないと思われる。加えて、他人に許諾された著作物の取扱いにおいて「実演」ないし実演家の創作の保護又は取締まりをすることの本来的な困難性により、衡平法裁判所ではほぼ不可能な監督上の問題が生じる。
著作権法とのさらなる衝突は、実演家の「セカンダリーミーニング」の認知が著作権者の潜在的な市場に及ぼす潜在的な制限である。もしライセンシー候補者が、当該楽曲を演奏又は歌唱したがゆえに不正競争による実演家の保護を主張する可能性のあるアーティストそれぞれに対して支払いをしなければならないとした場合、当該ライセンシーは完全に興味を失うほど思いとどまる可能性がある。最後に、・・・・・・連邦議会が連邦法上の保護を与えていないケースについて不正競争防止法による保護を認めることは、事実上、明確なパブリックドメインとしての利用を許容する連邦法上の保護期間の制限なしに、州法による著作権法的な利益を付与することになってしまう。
原審の判断を支持する。
【ちょっとしたコメント】
歌声と楽曲の組み合わせに対する保護と連邦著作権法との関係
本件は、エンターテイナーである原告の歌声だけでなく、その歌声と音楽、歌詞及び編曲の組み合わせをCMに利用することが不正競争に該当するか否かが争われ、これが否定された事例です。
楽曲との組み合わせではなく、声それ自体についての保護が問題となったMidler事件やLahr事件、Waits事件とは事案が異なると考えられます(下記リンク先ご参照)。これらの判決と比較して考えてみると、おもしろいかもしれませんね。
参考:関真也法律事務所/【米国判例メモ/パブリシティ権・声の権利】有名な歌手の声によく似せた他の人物の歌声をラジオコマーシャルに使用することは、当該歌手のパブリシティ権を侵害するか?(Waits事件)
原告は、本件のCMに利用された楽曲について著作権を保有していませんでした。それどころか、被告らは著作権者から適切な利用許諾を受けて当該楽曲をCMに利用していました。この状況において、前述のとおり、原告は自らの歌声と当該楽曲の組み合わせについて保護を求めたため、連邦法である著作権法による楽曲の保護と、カリフォルニア州法による不正競争からの保護との適用関係が問題となりました。この点に関する裁判所の判断が、不正競争防止法による声の保護を考えるうえで重要な意義があると思われます。
この点について、裁判所は、以下のような理由により、歌声と楽曲の組み合わせに対するカリフォルニア州の不正競争防止法による保護を否定しました。
(理由)
① 著作権の保護については連邦の著作権法が優先し、州法による請求は認められないこと
② 楽曲の著作権者以外のアーティストによる請求を認めると権利処理が複雑になること
③ 不正競争防止法による保護を認めると、一定期間経過後に著作物を自由利用とする連邦の著作権法の趣旨が損なわれるおそれがあること
日本法への示唆
まず、理由①については、米国における連邦法と州法との関係の問題であるため、日本法に関して直接参考になるものではなさそうです。
次に、理由②については、日本の著作権法では、実演家やレコード製作者を保護する著作隣接権があるため、米国法とは事情が異なる部分がありそうです。もっとも、歌手や俳優、声優等の「声」そのものを保護する場合、これはわが国の現行著作権法でも認められてはいないため、権利処理の複雑化に対する配慮が必要となる可能性はあると思われます。
最後に、理由③については、日本法においても検討が必要となりそうです。
著作権法にせよ著作隣接権にせよ、一定の保護期間が設定されているほか、保護の対象となる行為や詳細な権利制限規定が決められています。現行不正競争防止法によって「声」の保護を認めた場合、著作権法が定めた保護期間その他の制限を超えて保護を受けることになる可能性があるため、両法の適用関係を慎重に検討することが求められるかもしれません。
この点については、弊所の関真也が弁護士が日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会で行った『連続研究会 エンタテインメント産業と生成AI・ディープフェイク』の第2回報告でも検討していますので、ご参照ください。
いかがでしたか?
関真也法律事務所は、俳優・声優・歌手等やその所属事務所をはじめ、エンタテインメント産業で活躍される方々の権利について、日本国内外の実務や、法令・裁判例・学説等を踏まえ、理論的な基礎を伴った解決を提供するべく、継続的かつ積極的に、実務・研究・情報発信・政策提言等の総合的な活動を行ってまいります。近時注目が高まっている、生成AI・ディープフェイクに関わる「声の権利」の問題についても、以下のように研究活動を行っています。
参考:関真也法律事務所/【資料公開】『連続研究会 エンタテインメント産業と生成AI・ディープフェイク』第1回・第2回報告資料(日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会)
関真也法律事務所では、生成AIやディープフェイクの問題を含めて、漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽・芸能・クリエイター等のエンタテインメント、ファッション、XR・メタバース、デジタルツインやNFTその他web3に関する法律問題について、広く知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。
これらの法律問題に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。
《関連する弊所所属弁護士の著書》
《その他参考情報》
XR・メタバースの法律相談:弁護士・関真也の資料集